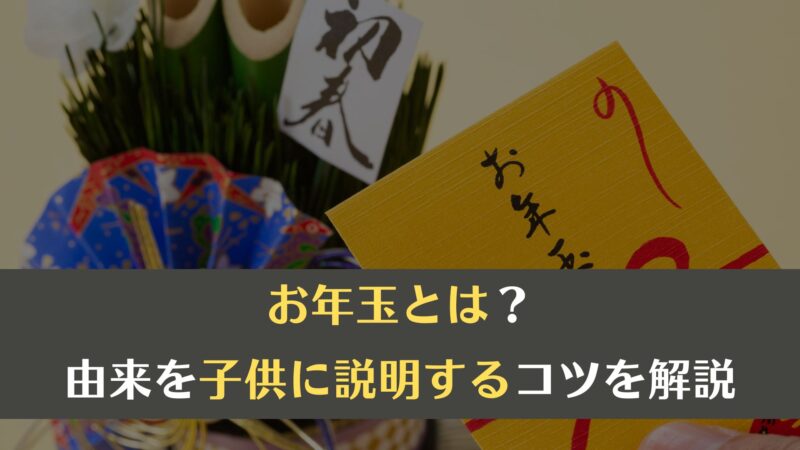「お年玉とは何なのか」「どういう由来があるのか」など、子供に聞かれた際にすぐ答えられますか?
昔ながらの習慣で、お正月には当たり前のようにお年玉を上げたりもらったりしていますよね。
しかしお年玉の起源は実はお餅だったということを知る人は、意外と少ないものです。
このページでは、お年玉の由来や意味を分かりやすくまとめています。
まずは親自身がお年玉についてしっかり理解して、「お年玉ってなに?」と子供に聞かれた際に分かりやすく説明できるよう備えておきましょう!
子供がお年玉に興味を持つタイミングは、子供のお金教育を始める良いきっかけにしやすいので逃さないようにしたいですね。
記事後半ではお年玉のマナーや相場を解説しているので、最後まで読んでお年玉を準備する際の参考にしてくださいね。
このページで分かること
- お年玉の由来は「御歳魂」
- お年玉について子供に説明するコツ
- お年玉を子供に管理させる方法
- 意外と知らないお年玉のマナー
- お年玉の相場
※当記事は2024年現在の情報になります。
※本ページにはPRが含まれます。
- 子供のお金教育にまつわる講座が満載!
- 講座実績が業界トップクラス!
- 親子で受けられる講座も充実!
\ 創業17年の実績! /
目次
お年玉とは?由来は「御歳魂」

お年玉の由来は諸説ありますが、「御歳魂」が由来でもともとは丸いお餅だったと言われています。
正月は歳神(年神)を家に迎えてもてなす期間で、お迎えすると家族に幸福をもたらすとされました。
御歳魂とは新年の神様である歳神(年神)を家に迎えるためにお供えされた、丸い鏡餅のことを指します。
お供えしていたお餅をお下がりとして、新しい一年の年初に家族に分配して食べることで神様から福を分けてもらえると信じられていました。
もともと歳神(年神)から分け与えられた御歳魂(お餅)は、目上から目下に渡す「お年玉」として受け継がれました。
高度経済成長期を背景にした昭和30年頃から、お年玉を現金で渡す人が増えてきたといわれています。

大人が子供にお年玉として現金を渡すのは、今や正月のメインイベントの一つとなっていますね。
お年玉について分かりやすく子供に説明するコツ

お年玉の由来を理解することで、ありがたみや感謝の気持ちが増します。
もらったお年玉を大切にできるようになるためにも、子供からお年玉について質問されたらきちんと答えられるように準備しておくとスムースですよ。
お年玉を子供に説明するコツは下記の通りです。
お年玉について分かりやすく子供に説明するコツ
- 物語調で聞かせる
- クイズ形式で教える
物語調で聞かせる
そもそも「説明」しようとすると、逆に難しくなってしまいがちです。
子供にとって分かりやすくお年玉について説明するには、物語調で聞かせるのがおすすめですよ。
物語調にすることで子供の記憶に残りやすく、感覚的に理解もしやすいです。
説明に自信がない人は、お年玉についての絵本もあるので活用しましょう!
クイズ形式で教える
クイズ形式にするなど、遊びの中に取り入れて説明することで子供が楽しみながら学べます。
遊びながらだと盛り上がりやすいですし、正解しようと子供が真剣に考えるというメリットもありますよ。
お年玉以外の質問にも使える方法なので、ぜひ子供とのコミュニケーションに取り入れてみてください!
お年玉に子供が興味を持ったタイミングでお金教育を始めると良い
いつからお金教育を始めれば良いのか、子供にとってのベストタイミングに迷う親は多いです。
そんな人は子供がお年玉に関する質問をしてくるなど、お金について興味関心を寄せ始めたタイミングでお金教育を始めるとスムースですよ。
ただしお年玉についての疑問にきちんと答えて、子供の興味を途切れさせないことが大切です。
子供からの質問に対して親が興味なさそうだったり、返答を適当だと感じると子供はそれ以上興味関心を持たなくなるかもしれません。
子供の疑問や質問にきちんと答えられるよう、ある程度事前にお年玉やお金に関する正しい知識を親自身も押さえておきましょう!

お年玉だけでなく、レジで会計している時やごっこ遊びの最中などでも、子供がお金に興味を持ったタイミングを逃さないようにしましょう。
お年玉を子供がスムーズに管理できるようになる秘訣3選

お年玉について子育て世代が抱える悩みの一つが、お年玉の管理方法です。
「お年玉はいつまで親が管理すべきなの?」「大金の管理を子供に任せても大丈夫…?」など、どうするのが子供にとってベストなのか悩みは尽きませんね。
基本的には子供が小学生になるとお年玉の一部を自分で管理させ始め、高校生になると全額自分で管理させる家庭が多い傾向です。
子供にお年玉の管理を任せるのを心配に思う親もいるでしょうが、お年玉を子供がスムーズに管理できるようになる秘訣を解説するので参考にしてください。
お年玉を子供がスムーズに管理できるようになる秘訣3選
- 子供の成長に合わせて自分で管理させる
- 欲しい物は自分で買わせる代わりに使い道には口を出さない
- お小遣い帳をつける習慣をつけさせる
①子供の成長に合わせて自分で管理させる
子供がお金の価値を理解できていない間は、親が全額管理しましょう。
子供名義の口座にお年玉を貯金していっている家庭が多いです。
子供が小学生に上がるタイミングを目安にして、少しずつ子供自身にお金の管理を任せるようにしてみましょう。
細かい時期については、子供の成長や性格に合わせると良いですよ。
最終的に子供が高校生になるタイミングでこれまでお年玉を貯めてきた通帳を子供に渡し、全額子供に管理させる家庭が多いです。
子供の頃からお金を管理する経験を積むことで、大人になって扱う金額が大きくなっても常識的な金銭感覚が身に付いてるので安心ですよ。
②欲しい物は自分で買わせる代わりに使い道には口を出さない
子供が欲しい物は自分で買わせて、お金の使い道にはなるべく口を出さずに見守りましょう。
子供は「自分のお金」を持つことで、お金と真剣に向き合うようになります。
自分が欲しい物と必要な物の区別がつくようになったり、お金が有限であることを理解して欲しい物を買うために貯金するなど、お金との正しい付き合い方が自然と身に付くようになります。
おもちゃやゲームなど欲しい物を買う満足感や、数年後に「なんでこんなものを買ってしまったんだろう」と後悔する気持ちなど…。
自分で考えて行動したうえで、お金にまつわる成功と失敗のどちらの体験も積み重ねることが重要です。
お金を無駄遣いしてないか心配になってしまうでしょうが、子供の自立心や金銭感覚を育てるためにもなるべく口を出さずに見守ってあげましょう。

「なんでこんなもの買ったの?」と親が口に出すのはやめましょう!
何気ない親の一言で、子供の好奇心や自立心の芽を摘んでしまう恐れがありますよ。
③お小遣い帳をつける習慣をつけさせる
子供にお金の管理をさせる際は、あわせてお小遣い帳をつける習慣を身に付けさせましょう。
お小遣い帳の内容は、親が定期的にチェックしてあげてください。
使い道にはなるべく口を出さないでおくべきですが、何にお金を使っているかを把握しておくなど子供に関心があることを示しましょう。
またお小遣い帳をチェックした際は、収支や残額が正しいかも確認してあげてくださいね。
お金の管理を子供の頃からしておくことで、「お金のセンス」が自然と身に付きますよ。
意外と知らないお年玉のマナー4選

お年玉を渡す時、押さえておくべきマナーがあります。
いざという時に恥をかかないためにも、下記4つのマナーを押さえておきましょう!
お年玉のマナー4選
- お札・硬貨のマナー
- ポチ袋のマナー
- 金額のマナー
- 目上の人には渡すのはNG
①お札・硬貨のマナー
お年玉用に新札と綺麗な硬貨を、事前に準備しておきましょう!
またお札の折り方や、硬貨を入れる向きにもマナーがあります。
お札の折り方は下記手順の通りです。
お札の折り方
- 肖像がある表面を正面に向ける
- 表面が内側に来るように左右を三つ折りにする
- 肖像が正面にある状態でポチ袋に入れる
硬貨は、表面を正面にしてポチ袋に入れるのがマナーですよ!
当たり前に思えるマナーですが、意外と抜けている人もいるので忘れないように気をつけましょう。
②ポチ袋のマナー
ポチ袋の表書きにもマナーがあるので、注意が必要です。
基本的に「お年玉」で問題ありませんが、渡す相手によって表書きを変える場合があります。
表書きのパターンを下記表にまとめたので、渡す相手によって正しい表書きにするよう参考にしてください。
| 渡す相手 | 表書き |
|---|---|
| 目上の人・目上の人の子供 (上司・上司の子供など) |
お年賀 |
| 両親・祖父母 | お年賀 |
| 小さい子供 | おとしだま |
後述で詳しく解説しますが、目上に渡したい場合は「お年賀」とするのがマナーです。
両親や祖父母など身内の場合も同様に、「お年玉」ではなく「お年賀」になりますよ。
また読み書きを始めたタイミングの小さな子供には、自分で読めるように表書きを「おとしだま」とひらがなにしてあげると喜んでくれますよ。

表書きはマナーは押さえておくのはもちろんのこと、ちょっとした配慮も加えると親切ですね。
③金額のマナー
お年玉の金額にもマナーはあります。
忌み数と呼ばれる「4」と「9」が付く金額は、死や苦を連想できるので避けてください。
400円や9,000円など、忌み数は避けておいたほうが無難ですよ。

お年玉だけでなく、忌み数を含む金額はお祝い金とはしませんよ。
④目上の人に渡すのはNG
お年玉の由来からも分かる通り、お年玉とは目上が目下に渡すものです。
そのため自分より年上または目上の人に、お年玉を渡すのはNGですよ。
その場合、お年玉ではなく「お年賀」としてください。
また上司の子供など、目上の人の子供へお年玉を渡す場合も同様です。
現金を渡すのは避けて、「お年賀」としてお菓子・図書券・ギフトカードなど品物を持参しましょう。
お年玉の相場はいくら?

お年玉の相場は、下記表の通りです。
| 年齢 | 相場 |
|---|---|
| 未就学児 | 1,000円未満 |
| 小学生 | 1,000円~5,000円 |
| 中学生 | 5,000円 |
| 高校生 | 5,000円~10,000円 |
| 大学生 | 10,000円以上 |
子供の年齢・子供との関係性・地域性によって、お年玉の金額は変動しやすいです。
あくまで相場の目安として、家族や親戚同士でお年玉の金額を決める際の参考にしてください。
お年玉をあげる対象の子供は、親戚内で年々増えていく可能性がありますね。
事前にしっかり話し合ってお互い納得のいく金額に設定しておくことで、不公平感や不満が生じにくくなります。
お年玉の相場に関する詳細や、いつがやめ時なのかを知りたい人は下記記事をご覧ください。
現金以外をお年玉としてもOK
「赤ちゃんへのお年玉は現金じゃなくて、おもちゃでもいいの?」
このように現金ではなく品物をお年玉として良いものなのか、疑問に思っている人もいると思います。
結論、現金以外をお年玉として渡しても問題ありません。
特に赤ちゃんの場合、図書券・ギフトカード・おもちゃを渡すと喜ぶ親は多いですよ。
もしも子供が食べられるお菓子を渡そうと考えている場合は、事前にアレルギーの有無を両親に確認しておきましょう!
上述の通り上司の子供など目上の人の子供に渡すお年賀も、現金ではなく品物にすると良いですね。
お年玉を子供に説明する方法は「キッズ・マネー・ステーション」の講座で学べる!
キッズ・マネー・ステーションのおすすめポイント
- 講座実績No.1の金融教育のパイオニア
- 子育て世代のための講座を提供
- 親子で楽しく学べるコンテンツが豊富
- オンライン受講が可能
キッズ・マネー・ステーションは日本の金融教育のパイオニアとして、講座実績No.1を誇ります。
子育て世代のための講座に参加して、子供のお金教育やキャリア教育への悩みを解消しましょう!
お年玉の管理方法や祖父母からのお小遣いの扱い方など、お金との正しい付き合い方を学べます。
さらに投資で資産形成する方法まで幅広く取り扱っているので、、お金についての知識を体系的に学べるのが強み。
親子で学べるコンテンツが豊富にあり、楽しみながらもお金の知識が自然と身に付くような内容となっています。
子供がお年玉に興味を持ったのを良いきっかけにして、子供にたくましく生きる力をプレゼントしましょう。
【まとめ】お年玉の説明を通してお金の大切さや感謝の気持ちを子供に伝えよう!
子供にお年玉について質問されたときスムーズに答えられるよう、事前に由来を把握しておきましょう!
子供に説明する時は、下記の工夫をすると子供が理解しやすいのでおすすめです。
- 物語調で聞かせる
- クイズ形式で伝える
お年玉について子供が理解することで、お金の大切さや感謝の気持ちも学べます。
そのほかお金について子供が興味関心を持ち始め時が、お金教育を始めやすいタイミングですよ。
いつ始めるべきか悩んでいた人は、子供の言動でタイミングを見極めましょう。
子供のお金教育のやり方が不安な人は、キッズ・マネー・ステーションの講座に参加して不安を解消してください!
オンライン講座も実施しているので、気軽に参加できますよ。